当事務所では、金融関連の許認可や金融コンプライアンスに関する業務を中心に取り扱っております。金融当局への申請手続のほか、各種届出、協会等の関連団体に関する入会手続や規程類の作成など社内体制整備のサポートについてお任せください。金融業務に関するコンサルティングやコンプライアンス研修のサポートも承ります。
また、遺言書や遺産分割協議書の作成、相続人の調査、相続財産の名義変更など相続手続に関するサポートにも力を入れております。相続全般に言えることですが、遺言書がない場合は特に、遺産の多寡にかかわらず、また普段は仲の良い親族間であっても、取得分や分割方法をめぐって大小の紛争が生じ得ます。遺言書の選択や記載内容のアドバイス、さらにはご希望に応じて遺言の執行までをサポートいたします。相続を見据えた生命保険の活用についてもご相談ください。
突然の相続で何から手を付けてよいのか分からないという場合、相続人や相続財産の調査方法が不明であったり、手続自体が煩雑でお困りの場合があるかもしれません。そのような場合に私が、相続手続の全体像をご説明し、相続人の皆様に代わって調査や手続を行い、遺産分割協議書の作成とその後に続く分割による財産の承継までをお手伝いいたします。
このほかにも、契約書や内容証明など権利義務・事実証明に関する書類の作成、金融以外の許認可や補助金の申請など多くの受任実績・対応経験がございます。取扱分野に記載した業務以外でも遠慮なくご相談ください。
金融商品取引業

金融商品取引業を行うためには、内閣総理大臣(財務局長等に権限が委任されています。)の登録を受けることが必要となります。近年、内部管理・法令遵守態勢の整備が強く求められており、登録審査は一段と厳しさを増している印象です。新規参入に当たっては、行おうとするビジネスの内容と方法を整理し、求められる態勢整備のレベルを見定め、適切に準備しておかなければなりません。
実務上、関係法令はもちろん、監督指針・ガイドライン・Q&A・パブリックコメント・協会規則なども重要な資料となります。業界の動きを追うように改訂の頻度も高いため、網羅的に内容を確認し、遵守すべきルールや考え方を細部まで押さえておかなければなりません。
ご相談者様の多くがフロント部門の熟練者であったり経営経験者であることから、成功事例に基づいたビジネススキームの検討は十二分になされているものの、内部管理部門、特にコンプライアンス・リスク管理関係は「この程度で大丈夫だろう」と軽く認識されているきらいがあります。また、中小規模の事業者様においては、現実的に内部管理部門に多くのリソースを割けない事情があるかもしれません。しかしながら、求められる態勢整備の目測を誤り準備を怠ると、申請手続が長期化するのみならず、金融当局の信頼を失い、立ち行かなくなることもあります。
私は、投資助言業者の立ち上げメンバーからその経営者に、その後、証券会社のコンプラインスオフィサーを経て士業に転向しました。実務を知るからこその「痒い所に手が届く」サービスの提供を実現したいと思っております。例えば、新規参入を目指す場合は、ビジネスの検討・整理段階における関与から登録完了までの全体的なサポートのご依頼のほか、お客様のご予算やご状況に応じて、アドバイザリー的に関与する、スポットで業務を補助するなど、業務範囲と深度を調整しお手伝いいたします。また、事業開始後にあっては、無料相談や軽微な業務対応を含む顧問契約のほか、規程類の整備、届出書の作成、提出代理、社内研修サポート、AML/CFT支援、内部監査・外部監査支援及び金融検査・協会監査・モニタリング対応補助など各種サービスを提供いたします。
その他金融商品仲介業、適格機関投資家等特例業務、電子決済等代行業、金融サービス仲介業、少額短期保険業、貸金業や暗号資産交換業など、金融庁又は財務局・財務事務所を窓口とする許認可全般を取り扱っております。協会やFINMACなど関連団体の入会等手続もお任せください。
遺言・相続
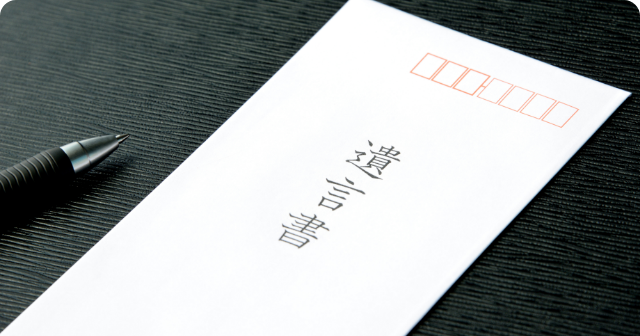
遺言書にはいくつか種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。手軽にできる「自筆証書遺言」か安全性の高い「公正証書遺言」かで迷われる方が多いのではないかと思います。遺言書を作成されるお客様のお気持ちをお伺いし、遺言書の選択をはじめ、「誰に」「何を」「どのくらい」承継させるため、「どのように」書き記すべきかなど、分かりやすくご説明いたします。
自筆証書遺言の場合は、そのデメリットが大幅に軽減されますので「自筆証書遺言書保管制度」のご利用をお勧めしております。公正証書遺言の場合は、公正証書原案の作成のほか、ご希望に応じて、公証人との調整、証人2名の手配と立会い、遺言書の保管サービスなどを行います。
遺言書によって誰に何をどのくらい承継させるのかを定めた場合、相続開始後、「誰が」遺言書の内容どおりに確実かつ適切に実行するかという問題が発生します。また、財産の売却や名義変更などにあたって専門的知識を要することもあります。そこで、「遺言の内容を実現する」という目的を果たすため、遺言書内で「遺言執行者」を指定しておくことができます。相続人同士のトラブルを未然に防ぐためにも、第三者的立場にある専門家を遺言執行者に指定しておいた方が良いでしょう。
私に遺言執行者をお任せいただくべきか、ご親族の中にふさわしい方がいらっしゃればその方のサポートに徹するべきかなど、お客様のご意向やご状況をお伺いした上で適切な提案をいたします。既に発生した相続で、遺言により遺言執行者に指定されている方、指定を委託されている方のサポートもお任せください。
相続手続においては、相続人の調査(戸籍等の収集)や相続財産(預貯金や株式等)の把握など分割協議に入る前の準備に手間と時間がかかることが多いと思います。令和6年3月1日から戸籍証明書等の「広域交付制度」が始まり、相続人ご本人による戸籍等の収集が容易になりました。しかしながら、行政書士などの士業や代理人による請求不可、郵送請求不可、兄弟姉妹の戸籍等は請求不可など、制度改善の余地はありそうです。
当事務所では、相続人や相続財産の調査から分割協議に基づく財産の取得までの相続手続全体のサポートのほか、部分的なご依頼もお受けしております。例えば、法定相続情報一覧図作成までのご依頼や遺産分割協議書の作成のみのご依頼でもかまいません。代襲相続や数次相続など複雑なケースについてもご相談ください。
近年、維持管理の負担軽減のために墓じまい(改葬)を検討されている方が増えています。墓じまいには墓地管理者とのやり取りや墓石の解体・撤去などのほか、行政手続(改葬許可)が伴います。自治体によって申請書の様式や手続が異なり、補助金を交付している場合もあります。当事務所は、全国の自治体に対応しております。墓じまいをお考えの方は、ぜひご相談ください。
生命保険

当事務所は、「日本生命保険相互会社(ニッセイ)」の代理店として同社の保険商品を取り扱っております。こちらは純粋な行政書士業務ではありませんが、金融関連業務でもあり、当事務所が取り扱う遺言・相続関係のお客様との相乗効果がありますので、取扱業務の一つとしております。
保険を選ぶ際、「自分に合った保険を選びましょう」ということがよく言われます。まず、お客様やそのご家族が、どのようなシーンで、どのくらいのお金に困るかを想像し、保険の「高さ(保険金額)」と「幅(保障期間)」を決めていくことが大切です。とは言っても、参考となるデータや比較対象などがなければ、お客様ご自身だけで決断するのは難しいかもしれません。周りに相談しても、資産状況など環境が異なるため、参考にならない場合も多いのではないでしょうか。
そこで、生命保険募集人として登録を受けている私が、近年の金融政策や社会保障制度などを踏まえて、お客様のライフステージで必要とされる「備え」を共に考え、業界最大手であるニッセイ独自のビッグデータを活用し「最適な保険プラン」をご提案いたします。
生命保険は、将来の万が一に備えるためだけのものではありません。保険金の非課税枠制度や受取人を指定することによる固有財産化など、相続税対策のためにも知っておきたい生命保険の活用方法を分かりやすく丁寧にご説明いたします。
生命保険が初めての方はもちろん、契約の見直しや乗り換えをご検討の方も、ぜひご相談ください。法人のお客様も歓迎いたします。
契約書・内容証明

法務に携わるようになって20年以上、契約書の作成とレビューを行ってきました。当事務所の強みは、単なる雛形の提供ではなく、ご要望を盛り込んだりご懸念を払拭するための条項を溶け込ませる反映力、個別具体的な事情に応じたカスタマイズが可能な点にあります。
売買、金銭消費貸借、業務委託といった一般的な契約以外にも特殊な契約のほか、協議書、合意書、示談書、覚書、念書、誓約書などの書類作成・レビューに対応いたします。
債権譲渡、クーリングオフ、消滅時効援用など内容証明に関しては、作成から郵送代行まで対応しております。代金や慰謝料などの支払請求、脱会通知など多数の実績がございます。
金融商品取引においては資産流動化の受け皿会社、ファンド組成に際しての資金調達などで合同会社が活用されることがあります。当事務所では、株式会社のほか合同会社の定款作成・認証やその変更等に伴う議事録の作成を取り扱っております。
なお、設立登記や変更登記が必要なケースにおいては、司法書士と共に対応させていただく場合、当初より司法書士をご案内する場合がございます。
約款や規程類の作成についてもお気軽にご相談ください。
古物商許可

古物の売買を事業として行う場合はもちろん、個人であっても副業としてフリマサイトなどで中古品の取扱いを行おうとする場合(いわゆる「せどり」)も、古物営業法に基づく許可を受ける必要があります。主たる営業所・自宅のある都道府県の公安委員会(所轄警察署)へ許可申請を行います。実際には、所轄警察署の生活安全担当課に出向き、許可申請書と添付書類を提出します。
なお、改正古物営業法(令和2年4月1日施行)により、既に許可を受けている古物商等が、他の都道府県に営業所等を設ける場合は、新設する旨の「変更届出」を事前に行うことで足りることとなりました。
当事務所では、法人個人を問わず、古物商許可の申請サポートを行っております。申請書類の準備・作成のほか、警察署への提出代理や各種変更届出も承ります。
帰化・永住許可

最近、多くのご相談をいただく帰化許可と永住許可ですが、これらは全く異なる制度です。両制度をご検討の方には、ご本人様のご希望、在留・就労状況などお伺いし、両制度のメリット・デメリット、許可要件や必要書類の違いなども含めご説明いたします。
また、許可申請の準備を進めるに当たっては、どの程度関与させていただくか(ご本人様自身でどの程度ご準備いただけるか)によって、業務内容が大きく変わってきます。この点もご本人様のご希望をお伺いしながら、関与の範囲と深度を調整いたします。






